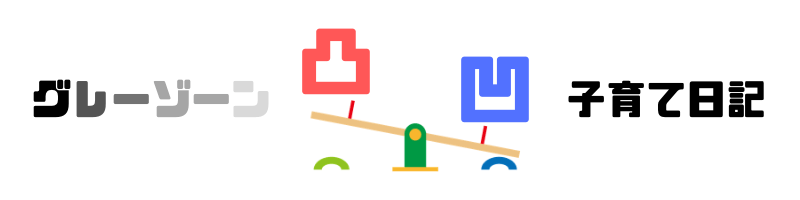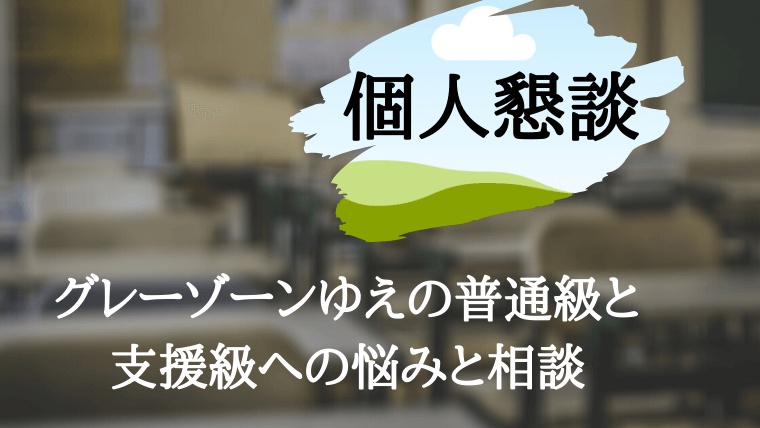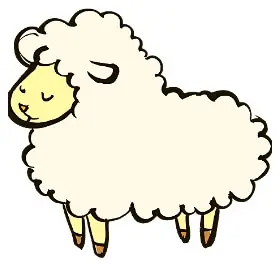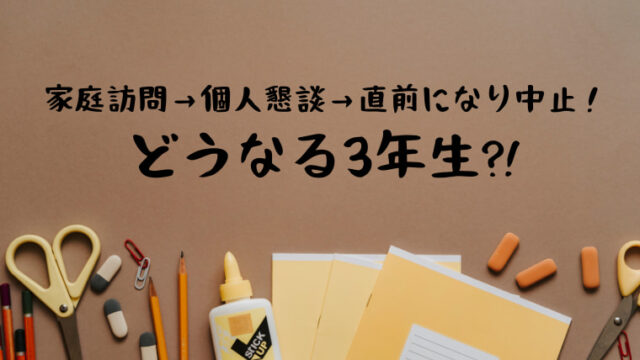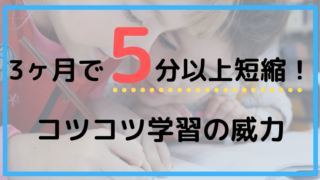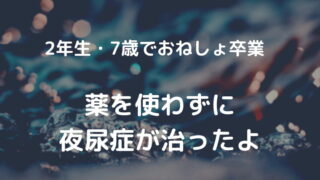12月半ば、希望者のみの2回目の個人面談が行なわれました。
今のそうたの現状は、学校での勉強・宿題に加えて、自宅ですららでの復習。
わからないと泣きながら、でも後ろに戻っては一歩ずつ前に進んでは何とか授業についていけている状態です。
普通級でもついて行くのがやっとならば、国語と算数だけでも自分のペースで取り組める支援級に行かせた方が良いのではないか…
ありがたいことに担任の先生はベテラン先生だったので、その辺も併せて相談することにしました。
目次
担任の先生から見た、息子の2学期の様子と1学期からの変化は?
夏休みの個人面談から約4ヶ月。
そうたの2学期の様子はというと、勉強の面では
- 先生の話を聴く姿勢がとても良い(他の子はだらけてしまう部分でも、そうたは先生の方を向いてしっかり話が聞けている)
- 支援員の先生にサポートしてもらいながら、周りの子と同じようなペースで授業が出来て来ている
- 聞き逃しがあっても周りの子の様子を見て真似をしたり、声をかけて聞いたりして同じように出来るようになった
勉強以外に関しては、
- 1学期は休み時間もひとりで教室で絵を描いたりして過ごしている事が多かったが、最近は友達と中庭に遊びに出かける事が多いようで、(先生が)気が付いた時には教室からいない事が多くなって来ている
ということでした。
友達とも段々と打ち解けて来ているようで、親としてはホッと一安心。
2年生では普通級で大丈夫?支援級の方が子供のため…??
学校の宿題をして、その後は時としてそうたを泣かせながらも、すららで復習。
子供のため…と言え、そこまで必死に頑張らせる必要があるんだろうか。
先生の前でついつい本音がポロポロと出てしまいます。
支援級に在籍している子もいろんな子がいて、
- 子供本人が「別にどっちで勉強しても変わらないよ〜」と、親の進めるまま支援級で勉強している子
- 学年が上がって行くにつれて内容が難しくなって、いよいよ自分の中で勉強がわからないと自覚して支援級に入ってくる子
本当に様々なんです。
今はそうた君自身が、支援級に行きたくない!みんなと一緒に勉強したいという思いが強いので、無理に支援級に行かせるよりみんなと一緒に普通級で勉強した方が良いと思います。
普通級と支援級では学習内容にどのような違いがあるの?
普通級ではクラス全員が同じ内容を一斉にお勉強。
支援級はその子のペースや興味に合わせて…と春頃に学校から頂いたプリントには書いてあったけれど、実際にはどのくらい勉強内容が違うのかよくわかりません。
それに一度支援級に行ってしまったら、普通級には戻れないのでしょうか。
普通級 → 教科書の内容(基礎+応用)
支援級 → 教科書の内容(基礎のみ)
普通級でも支援級でも、同じ教科書の内容を勉強します。
ただ、普通級は基礎に加えて応用を勉強するんですが、支援級は応用は勉強せず基礎のみの勉強になります。
支援級に移った子は学年が上がっても支援級に在籍することが多いですが、支援級から普通級に戻れないわけではないのでそこまで心配される必要はないと思います。
もし支援級に行く可能性があるとすれば…3年生以降
学年が上がり勉強内容も徐々に難しくなっていき、授業について行けず支援級に移る子も多いそうです。
普通級で大丈夫だとか、支援級に移った方がいいなどの見極めはどうしたらいいのでしょうか。
2年生の授業の大きな山場は かけ算(九九)だけなので、2年生では十分授業についていけると思います。
ただ支援級に移る可能性があるとすれば、3年生以降ですかね。
3年生になると国語・算数に加えて、理科・社会・外国語活動という3つの科目の授業が増えます。
教育産業界では小学3年生は超重要学年と言われているそうで、【小4の壁】や【10歳の壁】とも言われるとっても大事な分岐点なんだそうです。
WISC-IV検査のボーダーラインの数値は【85】
話の流れで、保育園在園時に受けたWISC-IV(ウェイス・フォー)検査の話になりました。
WISC-IV検査では検査結果の分布が3分の2以上か、3分の1かに別れるボーダーラインの点数というものが存在します。
あくまでも【目安の数値】であるけれど、85がボーダーラインと言われています。
ただ85以下でも普通級で授業が出来ている子もいますし、85以上でも支援級で授業を受けている子もいます。
一つの目安が85と言われているんですよ。
自宅に帰りWISC-IVの検査結果の用紙を確認したところ、【89】でした。
今のところ、そうた本人は支援級で勉強することはサラサラ考えていないようなので、普通級での勉強が出来るだけ長く続けられるように、親としてもサポート出来ることはしていきたいなと考えています。